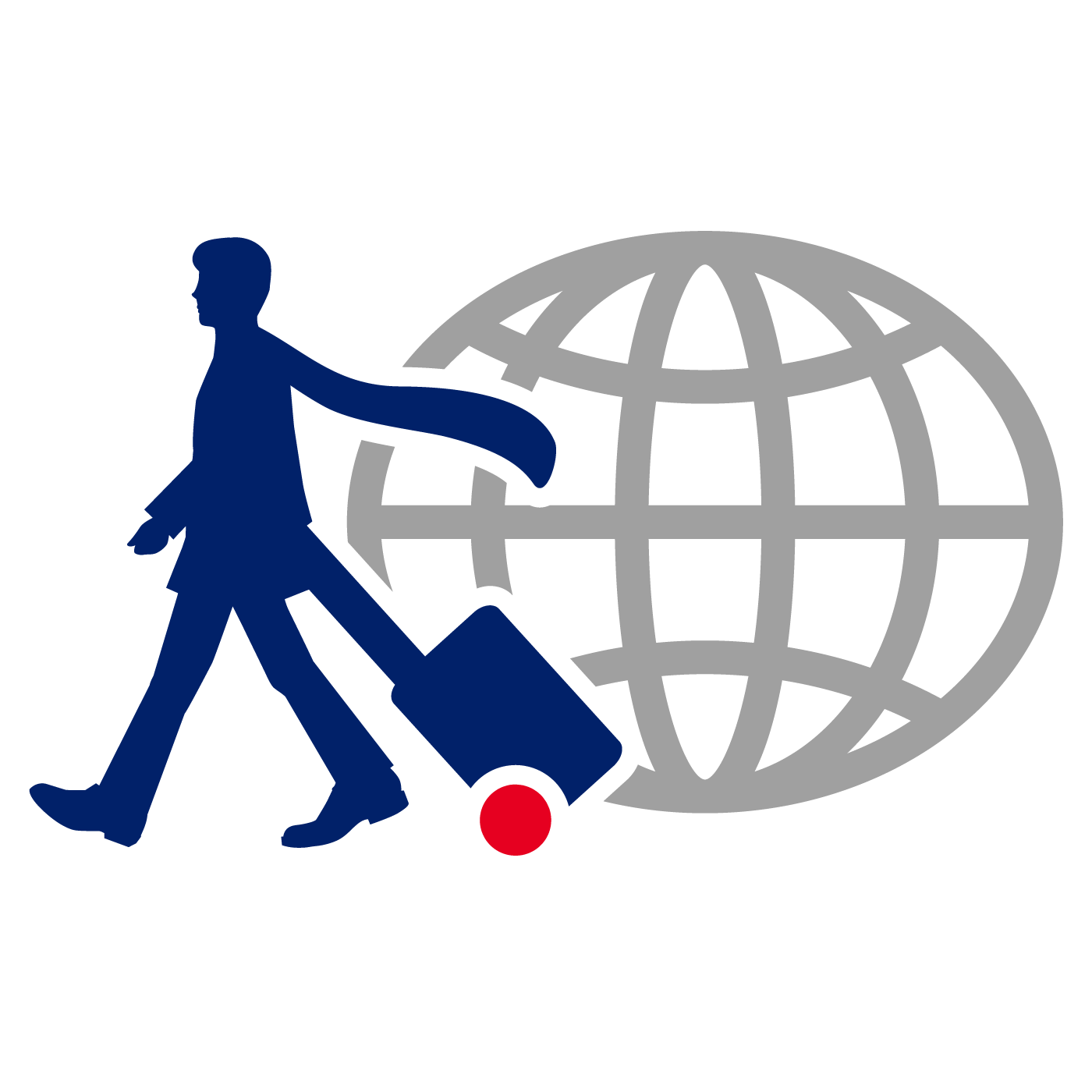あなたは、ヨーロッパを旅した時にチップを払ったことがありますか?
自分は、ヨーロッパにおいてはほとんどチップを払いません。
外食した時にカードで支払う際、チップを入力する欄がありますが、これも入れたり入れなかったりです。
ヨーロッパでのチップの習慣は昔とは違っています。
以前は、レストランの請求書に数ポンドや数ユーロを上乗せすることが一般的でしたが、現在では多くの国で、チップのパーセンテージを理解することがより重要となっています。
ハウスキーパーには毎日チップを渡すべきでしょうか。
タクシーの運転手にはどうでしょうか。
フランスのウェイターはしっかりとしたプロフェッショナルな賃金が支払われており、チップのために働くことはないと聞いたことがあるかもしれません。しかし、それはどの程度正しいのでしょうか?
チップをいくら払えばいいのか、チップの渡し方と同じくらい悩ましい問題です。
そこで、ヨーロッパでのチップの渡し方について、一緒に考えてみましょう。
イギリス人の妻の見解も含め、どのようにするべきなのか、お伝えします。
日本人初のBoardingAreaオフィシャルブロガー PAR@Seasoned Travellerです。
[toc]
レストランでは、いくらぐらいチップを払えばよいのか?
ヨーロッパで外食する場合、もちろんお店の質やサービスのレベルにもよりますが、税抜請求額の10%から15%を目安にチップを渡すとよいでしょう。
ですが、接客業に従事する人々の賃金が一般的に高い国では、チップの額を下げても大丈夫です。
例えばデンマークでは、スタッフは他の国のようにチップを期待していません。
デンマークにはチップの文化がないようです。
その代わりに、チップは個人の自由のため、コペンハーゲンで食事をする人は、良いサービスを受けたら会計の10%をチップとして渡すのが一般的だそうです。
もちろん、模範的なサービスや、誰かがわざわざ手伝ってくれた場合、例えばおしゃべりなソムリエが、完璧に焼き上げたステーキに最適な赤ワインを探してくれた場合などは、北欧では15%、あるいは20%のチップを自由に置いてもいいそうです。
ヨーロッパ本土では、10%から15%が標準的なチップで、それ以上はボーナスと考えてよいでしょう。
イギリス人の妻は、レストランにおいては、よっぽど良いサービスを受けない限りはチップは払っていません。
既にサービス料として含まれているケースがほとんどなのもありますが、今までチップを払ったのを見たのは9年で2回程度です。
請求書にサービス料が加算されている場合でも、チップを払うべきか?
請求書に目を通し、サービス料(通常12.5%から15%)があった場合、通常はチップを追加する必要はありませんが、お釣りを少し残しておくと喜ばれるでしょう。
フランスでは、法律によりレストランでは15%のサービス料が請求書に自動的に加算されますが、しっかりとしたサービスには2〜3ユーロの小銭を残すのが一般的です。
フランスではウェイターという職業は、他の多くの国よりも専門的な職業として広く認識されており、そのため、スタッフの基本給も高く設定されています。
そのため、アメリカのように熱狂的に飲み物を補充してくれるサーバーを見かけることはほとんどありません。
サービス料が請求書に含まれている場合、チップを渡す必要はないかもしれませんが、すべてのレストランが「サービス料」の使途を明示しているわけではないことは知っておいた方が良いでしょう。
チップはカードより現金で渡すのがよいのか?
チップに関しては今でも現金が王道のようです。
カードで支払いをする場合、チップを追加する機能があれば、チップをまったく残さないよりも、追加したほうがよいでしょう。
さらに良いのは、滞在の終わりにチップ用に十分な現金を用意しておくことです。
ヨーロッパでタクシー運転手にチップを渡すべきか?
デンマークではタクシー運転手にチップを渡す習慣はありませんが、実際、ほとんどのヨーロッパ諸国では、タクシーに乗るときにチップを渡すことは必須ではありませんが、感謝されることが多いようです。
もし、特別なサービス(観光のヒント、大きなバッグやスーツケースをトランクに積むのを手伝ってくれるなど)に出会ったら、ぜひお返しをすると良いでしょう。
ただし、観光地のタクシーは、他の地域よりも仕事が安定しており、料金もやや高めなので、多額のチップを渡す必要はありません。
この点、妻は、イギリスでタクシーに乗る時は積極的に払っています。
タクシー運転手があまり厚遇ではないこと、Uberなどのカーシェアリングサービスに押されて苦境に立たされているから、というのが理由だそうです。
タクシーの支払いは主にクレジットカードですが、端末にチップのパーセンテージを入力する欄があるので自分は妻に任せています。
ヨーロッパのホテルでは、ハウスキーパーにチップを渡すべきか?
ハウスキーパーには常にチップを渡すのが通常のようです。
ハウスキーパーという職業は、最も給与の低いホテルスタッフの一人で、十分な現金報酬をゲストから得られない傾向にあります。
一般的に良いホテルでは、毎日チップを渡すかどうかにかかわらず、素晴らしいサービスを受けることができます。
そのため、滞在の最後に一括で渡すのが一般的のようです。
ホテルによってはチップ用の封筒を用意しているところもありますが、ない場合はテーブルに置いておくとよいでしょう。
この点、妻は「払う必要はない」と言って頑としてチップを置いていきません。
ホテルのポーターには、いくらチップを渡せばいいのか?
もし、あなたのバッグやスーツケースを2階まで運んでくれたホテルの従業員の隣に立つことになったら、バッグ1つにつき1ユーロから2ユーロのチップが相場です。
迷ったら、地元の人を真似る
旅行先で他のテーブルを見ると、現地の人はチップをあまり払わないことに氣づくかもしれません。
では、ローマでは現地の人と同じようにチップを渡すべきなのでしょうか?
イタリアではチップに厳密な決まりはなく、むしろ礼儀として渡すものだそうです。
チップを渡すかどうかはお客様次第で、必ず渡すものではありません。
フランスと同様、イタリアでもチップ文化がそれほど浸透していない理由のひとつは、レストランやカフェでは最初からサービス料(servizie)やカバーチャージ(coperto)が含まれていることが多いからです。
氣まずくならずにチップを渡すには?
現金でチップを渡すときに、気まずい思いをしないようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
これだけ頭の中に入れておけば良いでしょう。
・お金を予め用意しておき、ポケットやバッグ、財布の中を探さない
・右手で折り畳んだ紙幣や硬貨を差し出し、笑顔でお礼を言うだけでよい
またチップを渡すときは、小額紙幣か高額硬貨を用意しておくと良いでしょう。
ポケットの中の小銭を適当に取り出して、相手の手に持たせるのは失礼にあたります。
また、財布の中から50ユーロ札を取り出し、「申し訳ありませんが、小銭がないようです」と言うのも失礼にあたります。
まとめ
日本においてはチップの文化がないのであまりイメージが湧きませんが、優れたサービスにはしっかりチップを、というのが世界的な考え方です。
可能な限り、現金で渡すようにしましょう。
逆に、ひどいサービスには全くチップを払う必要はありません。
インドで、タクシーに乗っている間ずっとどうでも良い話をされて、おりた時に「チップちょうだい」と言われたことがありました。
インド人は、話をすることを「良いサービス」と考えるようです。
何よりも、礼儀正しくあることが大切です。
チップを「払わされる」という感覚ではなく、その相手なりの「サービス」を意識して受け取ってみようと考えると、チップに対する考え方も少し変わるかもしれません。
ただ自分は、インドのあのおしゃべりサービスにチップはどうしても払えません・・・。